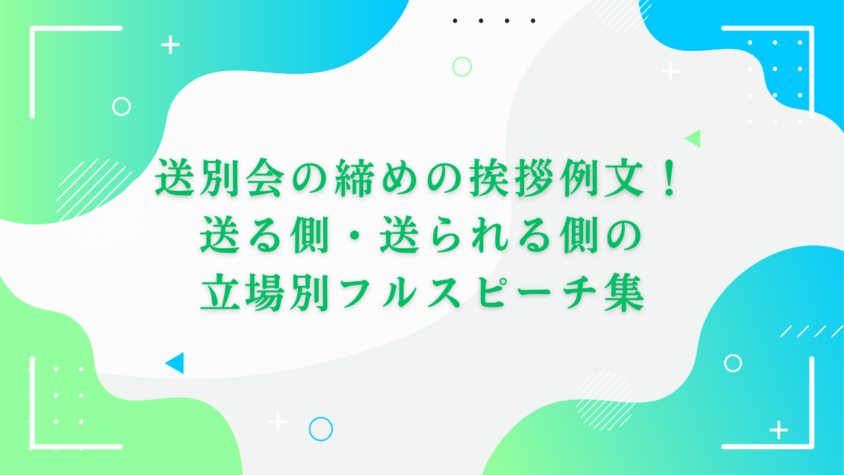送別会の締めの挨拶を任されると、「何を話せばいいのか」「どのくらいの長さでまとめるべきか」悩む方は多いものです。
この記事では、送る側・送られる側それぞれの立場に合わせたフルバージョン例文を豊富に掲載しています。
フォーマルな場面からカジュアルな会まで、どんな状況でも自然に使える構成になっているので、初めての方でも安心して準備ができます。
また、一本締めや乾杯の進行マナー、締めの挨拶を成功させるコツも分かりやすく解説。
この記事を読むだけで、送別会の最後を美しく締めくくるスピーチが完成します。
送別会の締めの挨拶とは?まず知っておきたい基本マナー

送別会の締めの挨拶は、単なる形式ではなく「その場を美しく締める大切な役割」を持っています。
ここでは、まず基本のマナーや話す順番、そして誰がどのように話せば印象的になるのかを整理していきましょう。
これを理解しておくと、急に任されても落ち着いて対応できます。
締めの挨拶の目的と役割
締めの挨拶の目的は、送別会の空気を穏やかにまとめ、出席者全員が「良い会だった」と感じて帰れるようにすることです。
つまり、単に言葉を述べるだけではなく、その場の雰囲気を整える司会的な役割も含まれます。
締めの挨拶は“感謝・労い・未来へのエール”の3要素で構成すると失敗しません。
| 要素 | 内容のポイント |
|---|---|
| 感謝 | 送別される方へのお礼を一言添える |
| 労い | 一緒に過ごした時間や努力を称える |
| 未来へのエール | これからの活躍を前向きに応援する |
話す順番と時間の目安
送別会では、話す順番や時間の取り方にもマナーがあります。
一般的な流れは次のとおりです。
| 順番 | 話す人 | 目安時間 |
|---|---|---|
| 1 | 送られる本人 | 3分前後 |
| 2 | 送る側(上司・同僚など) | 2〜3分 |
| 3 | 幹事・司会(締めの挨拶) | 1分程度 |
長すぎる挨拶は印象を弱めてしまうことがあります。
時間配分を意識して、簡潔にまとめましょう。
緊張せずに話す3つのコツ
挨拶の途中で緊張してしまうのは自然なことです。
以下の3つを意識するだけで、落ち着いて話せるようになります。
| ポイント | コツ |
|---|---|
| ① 姿勢 | まっすぐ立ち、手は体の前で軽く組む |
| ② 視線 | 送別される方と参加者の両方に順番に向ける |
| ③ 間の取り方 | 文の区切りで2秒程度の間を取ると聞きやすくなる |
この3つを守ることで、落ち着いた印象を与えられます。
話す内容よりも、ゆっくり・丁寧に話す姿勢が信頼感につながります。
以上が、送別会で締めの挨拶をする際に押さえておきたい基本マナーです。
送られる側の締めの挨拶フル例文集【立場別】

送られる立場での締めの挨拶は、これまで支えてくれた人への感謝と、新しい一歩への決意を伝える時間です。
形式にとらわれすぎず、心のこもった言葉を選ぶことで印象深い挨拶になります。
ここでは立場ごとに使えるフルバージョン例文を紹介します。
① 定年退職する人の挨拶(フォーマル・カジュアル)
【フォーマルな場面での例文】
「本日は、私の退職に際しまして、このような場を設けていただき、誠にありがとうございます。
入社以来、約40年の年月をこの会社で過ごすことができたのは、支えてくださった皆様のおかげです。
とりわけ、部署の仲間たちとは多くの困難を乗り越え、たくさんの思い出を共有することができました。
これからは第一線を退きますが、ここで学んだ経験を大切にし、穏やかな日々を過ごしていこうと思います。
皆様の今後のご活躍と、会社のさらなる発展を心よりお祈り申し上げます。
長い間、本当にありがとうございました。」
【カジュアルな場面での例文】
「今日は、こんなに温かい会を開いていただき、ありがとうございます。
気がつけば40年、たくさんの方と関わりながら、あっという間の時間でした。
特に思い出深いのは、皆さんと一緒に取り組んだプロジェクトや、日々の何気ない雑談の時間です。
これからは少しゆっくりしつつ、これまでとは違う形で皆さんを応援していきたいと思います。
どうかお身体に気をつけて、これからも頑張ってください。
本当にお世話になりました。」
| 話の構成 | ポイント |
|---|---|
| 冒頭 | 感謝の言葉で始める |
| 本文 | 思い出や印象的な出来事を簡潔に述べる |
| 結び | 今後への前向きな言葉で締める |
② 転勤・異動の挨拶(上司/同僚/部下バージョン)
【上司として転勤する場合】
「このたび、異動の辞令を受け、新しい部署に移ることになりました。
本日はこのような温かい送別の場を設けていただき、心より感謝申し上げます。
在籍中は、皆さんと共に目標を追いかけ、日々多くの学びを得ることができました。
新しい環境でも、この経験を糧に、誠実に職務に励んでまいります。
今後とも、皆さんのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。」
【同僚として転勤する場合】
「本日は私のためにお集まりいただき、ありがとうございます。
この職場で過ごした時間は、私の社会人生活の中でも特に濃く、かけがえのないものでした。
新しい場所でも、皆さんから学んだ姿勢を大切にして、一歩ずつ成長していきたいと思います。
またお会いできる日を楽しみにしています。
これまで本当にありがとうございました。」
【部下として異動する場合】
「お忙しい中、このような場を設けていただき、ありがとうございます。
入社してから今日まで、多くの先輩方に支えられながら成長することができました。
新しい部署では未知の業務も多いですが、ここで学んだ経験を糧に挑戦していきたいと思います。
これからも変わらずご指導いただければ幸いです。
本当にありがとうございました。」
③ 退職・転職する人の挨拶(感謝+決意構成)
「本日は、私の退職に際し、このような会を開いていただきありがとうございます。
入社以来、さまざまな経験を通して多くのことを学ばせていただきました。
失敗のたびに支えてくださった上司や、励まし合った同僚の存在があったからこそ、ここまで続けることができたと思います。
次の環境では新しい挑戦が待っていますが、ここで得た教訓を忘れずに進んでいきたいです。
皆様の今後のご健勝をお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。」
④ 短くて使いやすい「2分以内の例文」
「本日はこのような送別の場を設けていただき、ありがとうございます。
これまでのご指導とご支援に、心から感謝申し上げます。
新しい環境でも、この経験を活かして頑張っていきたいと思います。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。」
| 時間 | 構成 | ポイント |
|---|---|---|
| 2分以内 | 感謝 → 経験 → 未来 | 短くても印象が残る構成 |
送る側の締めの挨拶フル例文集【上司・同僚・部下別】
送る側の挨拶は、会の雰囲気をまとめると同時に、送別される方の人柄や功績を伝える大切な役目です。
立場によって言葉のトーンや構成を変えることで、より心に響く挨拶になります。
ここでは、上司・同僚・部下を送る立場別に、すぐ使えるフルバージョンの例文を紹介します。
① 定年退職する上司を送る挨拶(フォーマル・カジュアル)
【フォーマルな場面での例文】
「本日は、〇〇部長の定年退職に際しまして、このような会を開催することができ、大変光栄に思います。
部長には長年にわたり、私たち若手の育成に尽力していただきました。
特に印象に残っているのは、プロジェクトが難航した際に部長が見せてくださった冷静な判断力と、私たちへの信頼の姿勢です。
そのおかげで、チーム全体が最後まで前向きに取り組むことができました。
部長のご指導のもとで学んだことは、私たちの財産です。
これからは少し肩の力を抜いて、ご自身の時間をゆっくりと楽しんでいただければと思います。
長年のご尽力に、心より感謝申し上げます。」
【カジュアルな場面での例文】
「今日は、〇〇部長のために多くの方々が集まってくださいました。
部長には仕事面だけでなく、人として多くのことを教えていただきました。
時には厳しく、でも常に温かく見守ってくださったことを、心から感謝しています。
休日の話題など、部長の意外な一面に触れるたび、仕事の疲れがほぐれたものです。
これからもお元気で、たまには私たちの近況を見に来てください。
本当にありがとうございました。」
| 構成要素 | ポイント |
|---|---|
| 感謝 | 在職中の支援・指導へのお礼 |
| 思い出 | 印象的な出来事を一つ取り上げる |
| 結び | 今後への労いと敬意を伝える |
② 転勤・異動する同僚への挨拶
【フォーマルな場面での例文】
「本日は、〇〇さんの送別会に多くの方が集まってくださいました。
〇〇さんとは同じチームで約5年間、一緒に仕事をしてきました。
どんなに忙しい時でも笑顔を絶やさず、周囲を明るくしてくれた姿が印象的です。
新しい職場でも、その前向きさと誠実さで、きっと多くの方に信頼されることと思います。
またいつか一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。
今まで本当にありがとうございました。」
【カジュアルな場面での例文】
「今日は〇〇さんの送別会ということで、チーム一同、少し寂しい気持ちです。
〇〇さんには仕事の合間にたくさん笑わせてもらいましたし、チームの雰囲気づくりにもいつも一役買ってくれました。
転勤先でもその明るさで、きっとすぐに新しい仲間に慕われると思います。
私たちは、〇〇さんから学んだ“前向きさ”をこれからも大切にしていきます。
またいつでも戻ってきてくださいね。」
| キーポイント | 説明 |
|---|---|
| 思い出 | 共有したエピソードを簡潔に |
| メッセージ | 今後へのエールを込める |
③ 退職・転職する部下を送る挨拶
「本日は、〇〇さんの送別会にお集まりいただきありがとうございます。
〇〇さんとは3年間、一緒に仕事をしてきました。
最初は戸惑いも多かったと思いますが、地道な努力を重ね、今ではチームに欠かせない存在になりました。
何事にも前向きに取り組む姿勢に、私自身も学ぶことが多かったです。
新しい環境でも、持ち前の明るさと真面目さで、さらに成長されることを期待しています。
またお会いできる日を楽しみにしています。
これまで本当にありがとう。」
| 話の流れ | ポイント |
|---|---|
| 冒頭 | 感謝と場の挨拶 |
| 中盤 | 成長・努力への評価 |
| 締め | 未来への応援と一言 |
④ 時間がないときの簡潔スピーチ(1分以内)
「本日は、〇〇さんのために多くの方にお集まりいただきありがとうございます。
これまで本当にお世話になりました。
新しい環境でも、〇〇さんらしく頑張ってください。
私たちはいつでも応援しています。
どうかこれからもお元気で。」
| 長さ | 使いやすさ | 場面 |
|---|---|---|
| 約1分 | 短くても印象に残る構成 | 終盤の締め挨拶に最適 |
場を美しく締める!一本締め・三本締め・乾杯の正しいやり方

送別会の最後を締めくくる際には、一本締めや三本締め、乾杯などの形式で場をまとめます。
どの方法を選ぶかで会の印象が変わるため、意味や進め方を知っておくと安心です。
ここでは、それぞれの正しいやり方と進行のポイントをわかりやすく解説します。
一本締め・三本締めの違いと意味
どちらも会を締めるための形式ですが、使い分けには意味があります。
まずは、それぞれの目的を理解しましょう。
| 種類 | 意味・目的 | 使用される場面 |
|---|---|---|
| 一本締め | 会をすっきりと終える締め方。短く整った印象。 | 送別会や式典の最後など |
| 三本締め | 大きな成果を祝う時に行う。より盛大な印象。 | 記念行事や式典の総まとめなど |
送別会では、落ち着いた印象を与える「一本締め」が最も一般的です。
一本締めの正しい進行
発声者(司会・幹事・上司など)が合図を出して全員で手拍子を行います。
進行の流れはとてもシンプルです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 発声者が「それでは、一本締めで締めさせていただきます」と宣言 |
| ② | 「よ〜お」の掛け声をかける |
| ③ | 全員で手を一回打つ |
「一本締め」は短く、全員の動作がそろうことで、会がきれいにまとまります。
静かな中に一体感を感じられる締め方です。
三本締めの正しい進行
「三本締め」は、一本締めよりも少し形式的な場に適しています。
拍手を三回繰り返すため、会全体を華やかにまとめたい時に向いています。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 「三本締めで締めさせていただきます」と宣言 |
| ② | 「よ〜お」と掛け声をかける |
| ③ | 「パン、パン、パン」と3回手を打つ |
| ④ | これを3回繰り返し、最後に「よ〜お」で締める |
テンポがずれると締まりが悪くなるため、発声者は掛け声を明確に行うことが大切です。
乾杯の進行マナーと声かけ例
送別会の締めでは、最後に「乾杯」で全員の気持ちをひとつにすることもあります。
発声者の言葉で全員が同じ方向に気持ちを向けると、自然にまとまった印象になります。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 「それでは、〇〇さんの新たな門出を祝して、乾杯いたしましょう」と呼びかける |
| ② | 全員の準備を確認 |
| ③ | 「ご唱和ください。乾杯。」と発声 |
短く明確な声かけが、会の流れをスムーズにします。
締めの言葉に迷ったときの便利フレーズ集
締めの挨拶で悩みがちな「最後の一言」。
下記のようなフレーズを使えば、自然に会を終えられます。
| シーン | 使える一言 |
|---|---|
| 送る側 | 「それでは、〇〇さんの今後のご活躍を願い、一本締めで締めさせていただきます。」 |
| 送られる側 | 「皆様の温かいお言葉を胸に、次の場所でも努力を続けてまいります。本日はありがとうございました。」 |
| 幹事 | 「これをもちまして、本日の送別会をお開きといたします。皆様、本日はありがとうございました。」 |
一言添えるだけで、丁寧で印象的な締めになります。
最後の言葉は“短く・明るく・前向きに”を意識しましょう。
会を盛り上げる締めの挨拶「+一言」例

締めの挨拶をより印象的にしたいときは、最後に「ひとこと」を添えるのがおすすめです。
少しの言葉で会場の空気をやわらげたり、温かい余韻を残したりすることができます。
ここでは、フォーマルな場面でも使えるものから、親しい間柄でのカジュアルな一言まで紹介します。
空気を和ませる軽いジョーク例
軽いユーモアを交えると、場の緊張をやわらげて和やかな雰囲気で締めくくれます。
ただし、相手をからかうような内容は避けましょう。
| シーン | 一言の例 |
|---|---|
| 職場の同僚を送るとき | 「〇〇さんがいなくなると、急に静かになりそうですね。たまには顔を見せてください。」 |
| 上司を送るとき | 「〇〇部長がいなくなると、私たちの相談相手がいなくなって困ります。どうか電話一本で助けてくださいね。」 |
| 仲の良いメンバー間 | 「〇〇さん、次の場所でも“伝説”を作ってください。私たちは遠くから応援しています。」 |
笑いよりも“温かい空気”を意識したジョークがベストです。
心に残る「最後のひとこと」の作り方
最後の言葉で印象を決めるのは、話の長さではなく「温度感」です。
たとえば、次のような一言を添えると、参加者の心に残る挨拶になります。
| 場面 | 使える一言例 |
|---|---|
| 送られる側として | 「皆さんと過ごした時間が、これからの私の支えになります。」 |
| 送る側として | 「〇〇さんのこれからの道が、より良いものであることを心から願っています。」 |
| 幹事として | 「この会を通して、〇〇さんの素敵な笑顔をたくさん見られて良かったです。」 |
“ありがとう”という言葉を中心にしたメッセージは、どんな場面でも好印象です。
フォーマルでもOKなユーモア入り例文集
少し笑いを交えたいけれど、かといってくだけすぎたくない――そんな時に使えるのが「フォーマルユーモア」タイプの挨拶です。
【例文①:転勤する上司を送る場合】
「〇〇部長は、いつも冷静で頼れる存在でした。
ですが、社内旅行でのユニークな一面は、私たちにとって忘れられない思い出です。
新しい場所でも、その柔らかさと力強さで皆を導いてください。
本当にありがとうございました。」
【例文②:退職する同僚を送る場合】
「〇〇さんと一緒に仕事をしてきた時間は、私にとって大きな財産です。
仕事の合間に見せるユーモアや、落ち着いた判断力に何度助けられたかわかりません。
次の職場でも、〇〇さんらしく穏やかな笑顔で頑張ってください。
今まで本当にありがとうございました。」
| タイプ | 使うポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| フォーマルユーモア | 「相手の良い面」を少し柔らかく表現 | 個人的・内輪的な冗談は避ける |
| カジュアルユーモア | 「思い出話+笑い」で場を締める | 名前を出す時は敬意を込める |
軽いユーモアを交えることで、会の雰囲気が和らぎ、自然な笑顔で締めくくることができます。
大切なのは“笑いよりも温かさ”。感謝と敬意が伝わる言葉を選びましょう。
送別会の締めの挨拶Q&A【リアルな疑問を即解決】

送別会の締めの挨拶は、形式的に見えて意外と奥が深いものです。
ここでは、よくある疑問をQ&A形式でまとめ、すぐに役立つ実践的なアドバイスを紹介します。
誰が締めの挨拶をするのが正解?
基本的には、送別会の主催者(幹事や上司など)が締めの挨拶を担当します。
ただし、送別される人の立場によって、次のように変わります。
| 送別される人の立場 | 締めの挨拶をする人 |
|---|---|
| 上司・管理職 | 幹事またはその上司 |
| 同僚・一般職 | 同じチームの代表者 |
| 部下・後輩 | 直属の上司や先輩 |
「関係が近い人」が担当すると、会全体に温かみが生まれます。
挨拶はどのタイミングでする?
締めの挨拶のベストタイミングは、会の流れが落ち着き、料理や歓談が一段落した後です。
全体の終了予定時刻の15〜20分前を目安に始めるとスムーズです。
| 会の流れ | 締めの挨拶の位置 |
|---|---|
| 開会挨拶 → 歓談 → メッセージ → 送別される人の挨拶 | その後に行う |
| 途中で中締めを行う場合 | 幹事が中盤で行う |
慌てて始めると全員の注意が向かないため、幹事と事前に確認しておくのが安心です。
挨拶の長さはどれくらいが適切?
長すぎる挨拶は集中力が切れやすく、短すぎると気持ちが伝わりにくくなります。
適切な長さは、会の規模によって次の通りです。
| 会の規模 | 目安時間 |
|---|---|
| 20人以上の公式な送別会 | 3〜5分 |
| 部署やチーム単位の送別会 | 2〜3分 |
| 小規模のカジュアルな会 | 1〜2分 |
話の構成を「導入→思い出→未来→締め」にすると、時間配分を守りやすくなります。
短くても“誠意と笑顔”が伝われば、それが一番の締めになります。
複数人を送る場合はどうする?
送別される人が複数いる場合は、全員に均等に感謝を伝えることが大切です。
一人ずつの紹介を長くする必要はなく、「共通の思い出」や「チームとしての言葉」を中心にするとバランスが取れます。
例文:
「本日は〇〇さん、△△さんのお二人の送別会に、このように多くの方が集まってくださいました。
お二人とは、それぞれ違う形で関わってきましたが、どちらも私たちにとって大切な存在です。
これからのご活躍を心からお祈りし、一本締めで締めさせていただきます。」
| ポイント | 意識すべき点 |
|---|---|
| 公平性 | 全員に等しく触れる |
| まとまり | 共通点を中心に話を組み立てる |
| 締め | 全体をひとつの言葉でまとめる |
マイクなし・小規模な送別会ではどうする?
少人数の場合は、あえて堅苦しい言葉を避け、目を合わせながらゆっくり話すと自然にまとまります。
声を少し大きめに、間をとりながら話すことで全員に伝わりやすくなります。
会の規模に合わせて“話し方のトーン”を調整するのが、上級者のコツです。
まとめ|心に残る挨拶にするための最終チェックリスト
送別会の締めの挨拶で大切なのは、「完璧に話すこと」ではなく「心を込めて伝えること」です。
話し方よりも、どんな気持ちを伝えたいかを意識することで、自然に印象に残るスピーチになります。
最後に、準備から当日までの流れをスムーズに進めるためのチェックリストを紹介します。
話の組み立て方|5ステップチェックリスト
話の流れを整理しておくことで、緊張しても焦らずに話せます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 冒頭で感謝を伝える |
| ② | 印象に残ったエピソードを一つ話す |
| ③ | 送別される方(または参加者)へのねぎらいを込める |
| ④ | これからの未来への一言を添える |
| ⑤ | 簡潔な締めの言葉でまとめる |
この順番を守るだけで、どんな場面でも自然な挨拶が完成します。
話す時の表情と姿勢のポイント
話の内容だけでなく、表情や姿勢も印象を左右します。
穏やかで落ち着いた雰囲気を意識するだけで、信頼感が高まります。
| ポイント | 具体的なコツ |
|---|---|
| 姿勢 | まっすぐ立ち、背中を伸ばす |
| 目線 | 送別される人と会場の両方を交互に見る |
| 声のトーン | ややゆっくり、明瞭に話す |
| 表情 | 微笑みを意識して穏やかな印象に |
無理に笑う必要はありません。自然な表情が一番伝わります。
最後に意識したい3つのポイント
締めの挨拶を成功させるためには、準備と心構えが大切です。
次の3点を意識することで、どんな場面でも安心して話せるようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 丁寧さ | 形式よりも気持ちのこもった言葉を意識する |
| ② 簡潔さ | 話を短くまとめて印象を残す |
| ③ 前向きさ | 明るい言葉で会を締める |
“感謝・労い・未来”の3つを意識するだけで、自然と良いスピーチになります。
締めの言葉テンプレート
最後の一言に迷ったときに、そのまま使える締めのフレーズを紹介します。
| 場面 | 締めの言葉 |
|---|---|
| 送る側として | 「〇〇さんのこれからのご活躍を心からお祈りし、これをもちまして締めの挨拶といたします。」 |
| 送られる側として | 「皆様の温かいお心に支えられながら、次の場所でも努力してまいります。本当にありがとうございました。」 |
| 幹事として | 「本日の送別会はこれで終了とさせていただきます。ご参加ありがとうございました。」 |
どの言葉も短く、明るい印象で終わるように設計されています。
送別会の締めの挨拶は、“完璧な文章”よりも“まっすぐな気持ち”が何よりの贈り物です。
自分の言葉で心を込めて話せば、それが最も印象に残るスピーチになります。