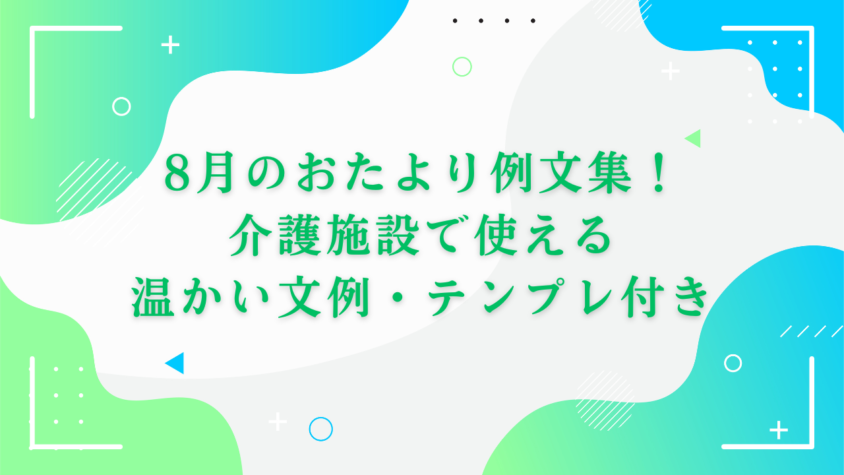8月のおたより、何を書こうか悩んでいませんか?
暑さの中で頭が回らず、「去年と同じになりそう…」と感じている方も多いはずです。
この記事では、介護施設やデイサービスでそのまま使える8月のおたより例文をたっぷり紹介します。
フォーマルからカジュアルまで、施設の雰囲気に合わせて選べる文例を揃え、“読まれる・伝わる・心に残る”おたよりづくりをサポートします。
さらに、季節の言葉やネタ集、タイトルの付け方まで、今日から使える実践テクニックも解説。
忙しい担当者でも、温かみのあるおたよりをスムーズに完成できるようになります。
8月の空気を感じる、あなたらしい一枚を一緒に作っていきましょう。
8月のおたより作成は「悩む月」?担当者のリアルな課題
8月は、一年の中でも特におたより作成が難しい時期です。
暑さで集中力が落ちる中、行事の準備やスケジュール調整など、やることが重なりやすい時期ですよね。
「書きたい気持ちはあるのに、筆が進まない…」そんな担当者さんも多いのではないでしょうか。
実は、8月は“情報をまとめにくい月”なのです。
行事も多く、施設全体が慌ただしくなるため、日々の出来事を落ち着いて整理する時間が取れません。
その結果、「気づいたら締切が明日」「内容が似てしまう」という状況になりがちです。
暑さ・お盆・イベントで“書く時間がない”問題
8月といえば、連日の暑さとお盆行事、そして夏祭りなど、行事が集中する時期です。
利用者さんやご家族に楽しんでもらうための準備が中心となり、おたより作成の時間が後回しになりやすいんです。
「気づいたら月末…」という声もよく聞かれます。
スケジュールに余裕を持たせることが、実はこの時期の最大のポイントになります。
| 時期 | やること | おたより作成のコツ |
|---|---|---|
| 8月上旬 | 行事準備・写真撮影 | 後で使えるよう、簡単なメモを残す |
| 8月中旬 | お盆対応・日常の記録 | 利用者さんのエピソードを少しずつメモ |
| 8月下旬 | おたより作成・校正 | テンプレートを活用して時短に |
「毎年似た内容になる」マンネリ化を防ぐには
8月のおたよりで多い悩みが、「去年と同じような内容になってしまう」というものです。
たしかに、同じ季節をテーマにしている以上、話題が重なりやすいですよね。
そこでおすすめなのが、“去年と同じ話題でも、切り口を変える”という方法です。
たとえば去年は「夏祭りの報告」を中心に書いたなら、今年は「準備の裏側」や「利用者さんの声」に焦点を当てるだけで、新鮮さが出ます。
同じテーマでも、伝える角度を少し変えることで、内容がぐっと豊かになります。
| 去年の内容 | 今年の書き方アイデア |
|---|---|
| 夏祭りの様子 | 準備に協力してくれた利用者さんの紹介 |
| お盆行事の報告 | 「思い出のひとコマ」として写真と一言コメントを添える |
| 暑さへのひと工夫 | 施設で取り入れている“涼を感じる工夫”を紹介 |
8月のおたよりで伝えたい3つのテーマ
8月のおたよりは、季節の移り変わりを感じさせつつ、読者に安心感や温かさを届けることが大切です。
そのために、意識しておきたいテーマを3つ挙げておきます。
- ① 季節の話題:向日葵や花火、蝉の声など、夏らしい風景を文章に取り入れる
- ② 日常のひとコマ:利用者さんやスタッフのやりとりを短く紹介
- ③ 感謝の気持ち:ご家族へのお礼や、日々の支援への感謝を言葉にする
8月のおたよりは、“情報を伝えるもの”から“想いを届けるもの”に変えるだけで、読まれ方が大きく変わります。
介護施設のおたよりに必要な基本構成と考え方
おたよりを上手に作るコツは、「型」を意識することです。
どんなに文章が得意でも、読む人が迷う構成では内容が伝わりにくくなります。
ここでは、介護施設のおたよりにぴったりな基本の3部構成と、読者に伝わりやすくするための考え方を紹介します。
読みやすい「3部構成(挨拶・本文・結び)」とは
多くの施設で親しまれているのが、「挨拶 → 本文 → 結び」という3部構成です。
この順番を意識するだけで、読みやすく、まとまりのあるおたよりになります。
| 構成部分 | 内容のポイント |
|---|---|
| 挨拶 | 季節のあいさつや、読者へのねぎらいの言葉を入れる |
| 本文 | 施設での出来事、利用者さんとの交流、行事の報告など |
| 結び | 感謝の言葉と、次月へのつながりを意識した一文 |
とくに最初の「挨拶部分」は、読者が“読むかどうか”を決める大切な導入部分。
「この施設のおたよりは、なんだか温かいな」と感じてもらうことで、最後まで読んでもらいやすくなります。
読者心理を意識したストーリー構成
おたよりの目的は「情報を伝える」だけではありません。
読者であるご家族や地域の方に、“施設での毎日をイメージしてもらうこと”が大切です。
そのために、ストーリー性を意識すると伝わり方が変わります。
- 【導入】 季節の挨拶で雰囲気をつくる
- 【展開】 日常や行事の様子をエピソードとして紹介
- 【締め】 感謝の言葉や来月へのひとことを添える
この流れを意識すると、「読む心地よさ」が生まれます。
まるで手紙を読んでいるような温かさが伝わるおたよりになります。
職員の声・利用者様の様子を効果的に盛り込むコツ
文章にちょっとした“声”を加えると、一気に生きたおたよりになります。
ここでいう声とは、スタッフや利用者さんの日常のひとことや表情のことです。
たとえばこんな一文を入れるだけで印象が変わります。
| 普通の表現 | 温かみのある表現 |
|---|---|
| 施設内で七夕を行いました。 | 「願いごとを書きながら、皆さん笑顔で短冊を飾っていました。」 |
| 工作レクを実施しました。 | 「“これ、孫に見せようかな”と嬉しそうに話す方もいらっしゃいました。」 |
ほんの一言でも、人の気配が感じられるだけで、おたよりの雰囲気がぐっと優しくなります。
読む人の心に残るおたよりは、“出来事”より“人”を描くことから生まれます。
【完全保存版】8月のおたより例文集(介護施設向けフルバージョン)
ここからは、実際にコピペで使える8月のおたより例文をたっぷりご紹介します。
フォーマル・セミフォーマル・カジュアルの3トーンで、施設の雰囲気に合わせて使い分けができます。
そのまま使ってもよし、少し手を加えて“うちの施設らしさ”を出してもOKです。
時候の挨拶・書き出し例(フォーマル/カジュアル別)
【フォーマル】
立秋とは名ばかりの暑さが続いておりますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
蝉の声が響く中、利用者の皆様は穏やかな毎日を過ごされております。
日頃より当施設の運営にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
【セミフォーマル】
毎日暑い日が続いていますね。
施設の庭では向日葵が元気に咲き、まさに夏本番といった雰囲気です。
利用者の皆さんも「花を見ると元気になるね」と笑顔で過ごされています。
【カジュアル】
8月に入り、夏の空がまぶしい季節になりましたね。
セミの声や夕立など、夏らしい風景があちこちで感じられるようになりました。
施設では、皆さんの笑顔があふれる毎日が続いています。
体調を整える工夫を紹介する例文
【フォーマル】
暑い日が続いておりますが、施設では快適にお過ごしいただけるよう室内環境に配慮しております。
こまめに休憩を取り、皆様が心地よく過ごせる時間を大切にしています。
【セミフォーマル】
厳しい暑さが続いていますね。
施設では、水分を取る時間をスタッフ同士で声を掛け合いながら設けています。
少し涼しい時間帯には、風通しの良い場所でお話を楽しむ姿も見られます。
【カジュアル】
暑い毎日ですが、皆さんお元気に過ごされています。
お茶を飲みながら「夏はやっぱりこうでなくちゃね」と話す声も聞こえてきます。
無理せず、ゆっくりと過ごしていきましょう。
行事・レクリエーション報告の例文(夏祭り・納涼会など)
【フォーマル】
先日開催いたしました納涼会では、利用者の皆様にご参加いただき、笑顔あふれる時間となりました。
浴衣姿で参加された方も多く、「久しぶりに着たのよ」と嬉しそうに話されていました。
スタッフ一同、皆様と楽しい夏のひとときを共有できたことを嬉しく思っております。
【セミフォーマル】
今月の夏祭りは、とてもにぎやかでした。
ヨーヨー釣りや輪投げなど、昔懐かしい遊びを楽しみながら、利用者の皆さんも童心に帰ったような笑顔を見せてくださいました。
「また来年も楽しみだね」という声があちこちで聞かれました。
【カジュアル】
夏祭り、すごく盛り上がりました!……と言いたいところですが、今年は暑さ対策のため室内での開催です。
それでも、うちわや提灯の飾りつけで夏気分は満点。
「金魚すくい懐かしい〜」と話す声がたくさん聞こえてきました。
お盆・高校野球・花火など季節行事の話題例文
【フォーマル】
お盆の時期を迎え、ご家族と再会を楽しまれる利用者様も多くいらっしゃいました。
「昔は家族みんなでお参りに行ったものよ」と懐かしそうに話される姿が印象的でした。
また、テレビでは高校野球の熱戦が繰り広げられ、皆さんで応援しながら夏を感じていました。
【セミフォーマル】
8月といえば、お盆と高校野球ですね。
テレビの前では、「頑張れ!」という声が飛び交い、まるで球場にいるような熱気でした。
夕方には花火の映像をみんなで見ながら、「きれいだねぇ」とゆったり過ごしました。
【カジュアル】
お盆休みの時期になりましたね。
施設では、家族の話や昔の夏の思い出で会話が弾んでいます。
「昔は庭で花火をしたのよ」なんてエピソードもたくさん聞かせていただきました。
心温まる「結びの挨拶」例文集
【フォーマル】
まだまだ暑さが続きますが、皆様におかれましてもお体にお気をつけてお過ごしください。
今後とも、皆様の毎日が穏やかで充実した時間となるよう、職員一同努めてまいります。
【セミフォーマル】
厳しい暑さももう少しの辛抱ですね。
9月には秋の行事を予定していますので、また皆さんと楽しい時間を過ごせるのを楽しみにしています。
【カジュアル】
夏の思い出がたくさんできた8月。
9月もまた、皆さんと笑顔で過ごせるように頑張ります。
これからも、どうぞよろしくお願いします。
【フルバージョン例文】丸ごと使えるおたよりテンプレート3選
① フォーマル(法人・特養・老健向け)
立秋を過ぎても暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
当施設では、8月5日に納涼会を開催いたしました。
浴衣姿でご参加くださった方々の笑顔が印象的で、夏らしい温かい時間となりました。
今後も、皆様が安心して過ごせる環境づくりに努めてまいります。
まだ暑さが続きますが、ご自愛のうえ、どうぞお健やかにお過ごしください。
② セミフォーマル(デイサービス・小規模多機能向け)
毎日暑い日が続いていますね。
今月の夏祭りでは、輪投げやヨーヨー釣りなど、懐かしい遊びを皆さんと一緒に楽しみました。
「若いころを思い出したよ」と笑顔を見せてくださる方も多く、職員にとっても嬉しい時間となりました。
暑さの中でも、皆さんが笑顔で過ごせるよう、これからも工夫していきます。
③ カジュアル(地域交流・小規模施設向け)
8月のおたよりをお届けします。
今月は、みんなで作った風鈴を飾って夏気分を味わいました。
「風が吹くといい音がするね」と笑顔があふれるひとときでした。
9月も楽しい時間をたくさん作っていきましょうね。
これらの例文をベースに、“自分たちらしい言葉”を少し加えるだけで、ぐっと魅力的なおたよりになります。
8月らしさを演出する“ネタと表現”アイデア集
おたよりを読んだときに「季節が伝わってくるね」と感じてもらえる文章には、共通の工夫があります。
それは、“言葉の温度”を変えることです。
ここでは、8月のおたよりをより豊かに見せるためのネタや表現アイデアを紹介します。
おたよりで使える季節の言葉・季語リスト
季節感を出すには、「8月らしい言葉」を自然に入れるのがコツです。
文の最初や見出しに入れるだけでも、印象が一気に変わります。
| カテゴリ | 言葉の例 |
|---|---|
| 気候・空模様 | 立秋、残暑、真夏日、入道雲、夕立、青空、涼風、蝉しぐれ |
| 自然・風景 | 向日葵畑、朝顔、百日紅(さるすべり)、蓮の花、夕焼け空、星の瞬き |
| 行事・文化 | お盆、夏祭り、盆踊り、花火大会、甲子園、終戦の日 |
これらの言葉をうまく組み合わせると、短い一文でも豊かな季節感を表現できます。
たとえば、
- 「入道雲が高くのぼる空を見上げながら、夏の訪れを感じています。」
- 「蝉しぐれが響く中、皆さんと涼やかな午後を過ごしました。」
- 「夕暮れに光る花火を眺めながら、“夏っていいね”という声が聞こえました。」
こうした描写は、読者に“情景を想像させる力”があります。
旬の食べ物・自然・風景の描写例
文章に食べ物や植物の話題を少し入れると、ぐっと親しみやすくなります。
難しいことは書かず、「季節を感じる日常のひとコマ」を伝えるのがポイントです。
| テーマ | 描写の例 |
|---|---|
| 果物 | スイカを前にして「夏が来たね」と笑う声が聞こえました。 |
| 野菜 | 昼食の時間には、色鮮やかなトマトやきゅうりが並び、食卓が夏の色に染まりました。 |
| 花 | 朝顔が窓辺を彩り、見上げるたびに心が和みます。 |
| 風景 | 夕方の空が少しずつ茜色に染まり、夏の終わりを感じる瞬間でした。 |
特に介護施設では、こうした身近な描写が利用者さんやご家族との心のつながりを生みます。
「あ、うちの庭にも朝顔が咲いたよ」など、会話のきっかけにもなります。
懐かしい夏の風物詩を会話に取り入れるコツ
8月は、誰にとっても思い出がよみがえる季節です。
おたよりに「懐かしい夏の話題」を少し加えるだけで、読者の心がほっと温まります。
| テーマ | 使いやすい話題の例 |
|---|---|
| 遊び | 金魚すくい、ヨーヨー釣り、かき氷、花火 |
| 暮らし | うちわ、風鈴、すだれ、夕涼み |
| 思い出 | 「昔は縁日に行くのが楽しみだった」などの回想話 |
こうした話題は、利用者さんとの会話を自然に広げてくれます。
「あのときの花火の音、まだ覚えてるよ」「風鈴の音を聞くと、夏を思い出すね」など、共感のきっかけにもなります。
“懐かしさ”は、おたよりを通じて読者と気持ちを共有できる最高のテーマです。
読まれるおたよりに変わる3つの書き方テクニック
おたよりを読んでもらうためには、単に内容をまとめるだけでなく、「言葉の伝え方」を工夫することが大切です。
この章では、誰でも簡単にできる3つのテクニックを紹介します。
ちょっと意識するだけで、読みやすさと温かさがぐっと変わります。
1. 言葉をやさしく、温かくする「語彙変換術」
おたよりを作成する際、つい“かたい表現”になってしまうことはありませんか?
たとえば「実施いたしました」「行いました」などの表現は、丁寧ですが少し距離を感じることがあります。
そんなときは、次のように少し言い換えてみましょう。
| かたい言葉 | やさしい言葉 |
|---|---|
| 行いました | みんなで楽しみました |
| 実施いたしました | ○○を行いました |
| 取り組みました | 一緒に挑戦しました |
| 確認いたしました | みんなで見てみました |
たった一語を変えるだけで、ぐっと親しみやすくなります。
読む人が“声に出して読める文章”を意識すると、自然とやわらかい文になります。
2. 写真やイラストで“伝わるビジュアル”に仕上げる
おたよりは文字だけでなく、「見る楽しさ」を加えることで印象が大きく変わります。
特に、利用者さんの笑顔や行事の風景など、日常の一場面を切り取った写真は大きな力を持っています。
| 項目 | おすすめポイント |
|---|---|
| 写真 | 自然な表情や手元の様子を撮ると温かみが出る |
| イラスト | 向日葵・花火・うちわなど、季節を感じる素材を使う |
| レイアウト | 写真を文中に小さく入れるだけでも視覚的に読みやすくなる |
また、撮影した写真を使う際には、事前にご本人やご家族に共有することを忘れずに。
「この写真、いいですね」と声をかけていただけるような一枚を選ぶと、おたよりがより心に残るものになります。
3. タイトルで印象を変える“ひと工夫”
タイトルは、おたより全体の“顔”です。
せっかく良い内容でも、「○月号」だけでは読者の目を引きにくくなります。
次のように少し言葉を足すだけで、ぐっと印象が変わります。
| 一般的なタイトル | 魅力的なタイトル例 |
|---|---|
| 8月号 | 「向日葵の季節に〜8月のおたより〜」 |
| 施設だより | 「夏を楽しもう!○○苑の笑顔日記」 |
| お便り | 「暑さに負けない毎日を〜今月のご報告〜」 |
ポイントは、「季節+感情」を意識することです。
「夏真っ盛り」「笑顔の毎日」「ひと息つく季節」などの言葉を組み合わせると、読者が“読んでみたい”と感じるタイトルになります。
タイトルは短くても、読む人の気持ちを動かす“入り口”です。
テンプレでは終わらせない!心が伝わるおたよりの作り方
たくさんの例文を参考にしても、「なんだか自分の施設らしくならない」と感じることはありませんか?
その原因は、“言葉の置き換え”ではなく、“想いの乗せ方”にあります。
この章では、テンプレートをそのまま使うのではなく、「自分たちの言葉」で伝えるおたよりに仕上げる方法を紹介します。
1. 例文を「自分の言葉」に変える3ステップ
おたよりの魅力は、文章のうまさではなく、“その施設らしさ”です。
以下の3ステップを意識するだけで、同じ内容でも全く違った印象に仕上がります。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ① 見本を選ぶ | 施設の雰囲気に近い例文を選ぶ | フォーマル/カジュアルを明確に |
| ② エピソードを加える | 利用者さんや職員のちょっとした出来事を入れる | 文章に“人の温度”を出す |
| ③ 結びで想いを伝える | 「感謝」「これから」「楽しみ」という前向きな言葉で締める | 印象に残る余韻を残す |
たとえば、こんなふうに変えると雰囲気が一気に変わります。
| 例文そのまま | 自分たちの言葉に変えた例 |
|---|---|
| 夏祭りを開催しました。 | 8月10日に夏祭りを行い、「久しぶりの輪投げが楽しかった」と笑顔で話す方もいらっしゃいました。 |
| 向日葵が咲きました。 | 施設の庭に咲いた向日葵を見て、「太陽みたいに元気だね」と笑い声があがりました。 |
どちらも同じ出来事ですが、後者のほうが“情景と感情”が伝わります。
2. 利用者様・ご家族の心を動かす小さな工夫
おたよりを通して最も伝えたいのは、「皆さんのことを大切に思っています」という気持ちです。
そのために、ちょっとした表現の工夫を入れてみましょう。
- 「〜していただきました」より「一緒に〜しました」 → 距離感を近く
- 「〜が印象的でした」より「〜が心に残りました」 → 感情が伝わる
- 「〜でした」だけで終わらせず、「〜と感じました」と一言加える
おたよりは、ただの報告書ではありません。
“施設とご家族をつなぐ手紙”と考えると、文章に自然な温かみが生まれます。
3. 「また読みたい」と思われるおたよりの共通点
毎月のおたよりで読者の心をつかむ施設には、共通点があります。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 語り口が一貫している | 毎号トーンが同じで、安心感がある |
| 職員の“目線”がある | 「利用者さんが」「ご家族が」ではなく、「私たちは」を入れている |
| 季節の変化を感じる | 冒頭や結びに季節の言葉が自然に使われている |
| 読者を意識している | 「ぜひご覧ください」「ご家族の皆様も」など、呼びかけがある |
こうした要素を毎号の中で少しずつ取り入れると、読者に「来月も楽しみ」と思ってもらえるおたよりになります。
“テンプレでは終わらないおたより”は、想いと人の気配でできています。
まとめ|8月のおたよりは“夏の思い出をつなぐ手紙”
ここまで、8月のおたよりを作成するためのコツや例文をたっぷり紹介してきました。
おたよりは、単なる情報発信ではなく、施設とご家族、利用者さんの“心をつなぐ架け橋”です。
季節を感じる言葉、笑顔が浮かぶエピソード、そして「また読みたい」と思える温かさ——。
そのすべてが、読む人の心に残るおたよりを作ります。
今日から実践できる3つのポイント
最後に、明日からすぐ使えるおたより作成のポイントを整理しておきましょう。
| ポイント | 具体的なアクション |
|---|---|
| ① 季節感を大切にする | 「入道雲」「向日葵」「風鈴」など、8月らしい言葉を文中にひとつ入れる |
| ② 人のエピソードを入れる | 利用者さんやスタッフの何気ない一言を1行添える |
| ③ 感謝で締めくくる | 「いつもありがとうございます」「来月もよろしくお願いします」で優しい印象に |
この3つを守るだけで、毎月のおたよりがぐっと心に残るものになります。
読者の笑顔が増えるおたよりづくりを始めよう
おたよりは、“読む人の生活の一部”です。
ほんの数分の時間でも、心がやわらぐような言葉や風景を届けられたら、それだけで十分価値があります。
「文章が苦手だから…」と気負わず、まずは1文から始めてみてください。
あなたの言葉が、誰かの一日を少しあたたかくする。
それが、8月のおたよりを書く一番の意味です。