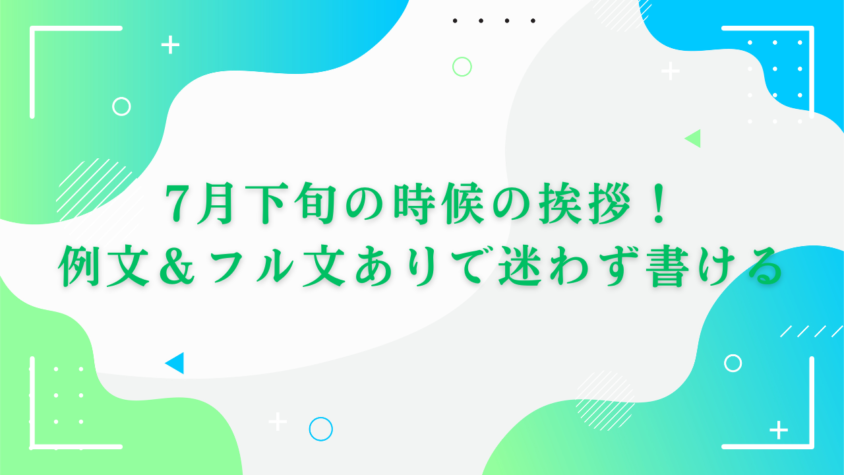7月下旬の手紙やメール、お中元のお礼状などで、「どんな挨拶を書けばいいの?」と悩んだことはありませんか。
実は、ちょっとしたコツを押さえるだけで、季節を感じさせる上品な挨拶文が簡単に書けるんです。
この記事では、7月下旬にふさわしい時候の挨拶を20パターン紹介します。
ビジネス・個人・カジュアルなど、シーンに合わせて使える例文をすべてフル文形式で掲載しました。
さらに、「大暑」「盛夏」「炎暑」などの使い分けや、相手に喜ばれる表現の選び方も丁寧に解説。
この記事を読めば、7月下旬の挨拶文に迷うことはもうありません。
手紙やメールに季節の彩りを添えて、相手に心が伝わる一文を作ってみましょう。
7月下旬の時候の挨拶とは?季節の背景を知ろう
7月下旬の時候の挨拶は、夏の盛りを感じさせる季節の言葉を選ぶのがポイントです。
この時期は、地域によって梅雨明けが進み、青空と強い日差しが印象的な時期ですね。
ここでは、7月下旬にぴったりな時候語や、その使い分け方を紹介します。
7月下旬はどんな季節?気候と時期の目安
7月下旬は、暦の上で「大暑(たいしょ)」にあたるころです。
一年の中でも特に暑さが厳しく、まさに夏真っ盛りといえる時期です。
この時期の挨拶文では、「暑さ」をそのまま言葉にするよりも、やわらかく伝えるのが上品です。
| 暦の節気 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小暑(しょうしょ) | 7月7日頃〜7月22日頃 | 暑さが本格的になる前段階 |
| 大暑(たいしょ) | 7月23日頃〜8月6日頃 | 一年で最も暑い時期 |
「大暑の候」や「盛夏の候」は、この時期を代表する表現です。
相手がどの地域に住んでいるかわからない場合も、これらを使えば全国どこでも違和感なく伝わります。
「大暑」「盛夏」「炎暑」などの意味と違い
7月下旬の時候の挨拶でよく使われる3つの言葉、「大暑」「盛夏」「炎暑」には、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
| 表現 | 意味・印象 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 大暑の候 | 暦の上で最も暑い時期を示す言葉 | ビジネス・公式文書に最適 |
| 盛夏の候 | 夏の盛りを表す穏やかな表現 | 幅広い相手に使いやすい |
| 炎暑の候 | 強い日差しや厳しい暑さを表現 | 少しくだけた挨拶や季節便り向け |
「大暑」はフォーマルに、「炎暑」は少し柔らかく、「盛夏」は万能タイプと覚えておくと便利です。
地域差による使い分けのポイント
7月下旬といっても、地域によって気候の印象は少し異なります。
たとえば、関東や西日本では真夏の暑さが本格化している一方で、東北や北海道ではようやく夏の兆しを感じる頃です。
そのため、気候の表現をやや穏やかにしたり、具体的な情景を添えると、より自然な印象になります。
| 地域 | おすすめの言葉 | 例文のトーン |
|---|---|---|
| 関東・関西 | 大暑の候・盛夏の候 | フォーマル・明るめ |
| 東北・北海道 | 炎暑の候・夏の盛り | 穏やかでやさしい表現 |
全国どこでも安心して使いたいなら「盛夏の候」がベストです。
時候語の使い分けを意識するだけで、文章全体の印象がぐっと洗練されます。
【完全保存版】7月下旬にふさわしい時候の挨拶フル例文集20選
7月下旬は、季節の挨拶が最も多く使われる時期のひとつです。
ここでは、ビジネス・知人・友人など、あらゆる場面で使える時候の挨拶を20パターンご紹介します。
フォーマルからカジュアルまで、コピペOKの例文をそのまま使えるように整理しました。
フォーマル(ビジネス・お礼状)に使える例文8選
フォーマルな表現は、取引先や目上の方、公式文書での使用に適しています。
漢語調でまとめると、格式のある印象を与えられます。
| 番号 | 例文 |
|---|---|
| 1 | 大暑の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 2 | 盛夏の候、皆様にはますますご健勝のことと拝察いたします。 |
| 3 | 炎暑の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 |
| 4 | 酷暑の候、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 |
| 5 | 大暑の候、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 6 | 盛夏の候、平素は格別のご厚情を賜り深く感謝申し上げます。 |
| 7 | 炎暑の候、日ごろのご支援に厚く御礼申し上げます。 |
| 8 | 酷暑の候、貴殿のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。 |
「大暑」「盛夏」「炎暑」「酷暑」は7月下旬にぴったりのフォーマル四大表現です。
どの表現も、時候の挨拶として違和感なく使えます。
セミフォーマル(お客様・知人宛て)に使える例文6選
ビジネスでも柔らかさを出したい時や、丁寧な印象を保ちたい個人宛ての手紙に適しています。
| 番号 | 例文 |
|---|---|
| 1 | 猛暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。 |
| 2 | 盛夏の候、日頃よりお引き立ていただき誠にありがとうございます。 |
| 3 | 大暑の折、平素より格別のご厚情を賜り心より御礼申し上げます。 |
| 4 | 炎暑の候、時節柄ご自愛くださいますようお願い申し上げます。 |
| 5 | 盛夏の折、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 |
| 6 | 酷暑の候、日々のご支援に心より感謝申し上げます。 |
「〜の折」や「〜の時節柄」という言い回しを使うと、ビジネスにも個人にも応用しやすくなります。
カジュアル(日常・友人宛て)に使える例文6選
親しい相手に送るときは、やわらかい言葉や季節の情景を交えると自然です。
絵文字や感嘆符を避けつつ、語りかけるようなトーンで書くのがポイントです。
| 番号 | 例文 |
|---|---|
| 1 | 毎日暑い日が続いていますが、お元気にお過ごしでしょうか。 |
| 2 | セミの声がにぎやかに響く季節になりましたね。 |
| 3 | 青空がまぶしい季節、いかがお過ごしですか。 |
| 4 | 夏の風を感じる今日この頃、元気でお過ごしでしょうか。 |
| 5 | 入道雲が浮かぶ空を見上げると、夏を実感しますね。 |
| 6 | 暑さが続いていますが、心穏やかにお過ごしください。 |
自然描写+相手への気遣い=親しみのある挨拶になります。
【フルバージョン例文】書き出し+本文+結びまで完成形3パターン
次の3つは、冒頭から締めくくりまで一通の挨拶文として完成させたフル例文です。
文全体の流れをつかむ参考にしてください。
| タイプ | フル例文 |
|---|---|
| フォーマル | 大暑の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 暑さ厳しき折、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 |
| セミフォーマル | 盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。
おかげさまで、私どもも変わらず元気に過ごしております。 暑い日々が続きますが、どうぞお体を大切にお過ごしください。 |
| カジュアル | セミの声がにぎやかに響く季節になりましたね。
暑さの中でも、元気に過ごしていらっしゃることと思います。 無理をせず、ゆっくり夏を楽しんでください。 |
ポイント: どの文も「季節の表現→相手の様子→結びの気遣い」という三段構成になっています。
この流れを守ると、自然で美しい挨拶文が完成します。
お中元・夏季休業・お知らせメールで使える7月下旬の挨拶
7月下旬は、お中元のお礼状や夏季休業のお知らせを出す時期でもあります。
この章では、実務でそのまま使える文例をフォーマル度別に紹介します。
シーンに合わせた言葉を選ぶことで、丁寧で印象の良い挨拶文になります。
お中元のお礼状で丁寧に伝える例文3選
お中元のお礼状は、受け取ってからなるべく早く出すのがマナーです。
感謝の気持ちを伝えつつ、暑中見舞いの要素を自然に取り入れましょう。
| タイプ | 例文 |
|---|---|
| フォーマル | 大暑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは心のこもったお中元の品を頂戴し、誠にありがとうございました。 皆様のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。 |
| セミフォーマル | 盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。
このたびはお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。 暑さ厳しき折、どうぞご自愛ください。 |
| カジュアル | セミの声が響く季節になりましたね。
素敵なお中元をいただき、ありがとうございます。 暑さが続きますが、どうぞ穏やかにお過ごしください。 |
注意:「お中元のお礼」は必ず感謝を明確に伝え、相手への気遣いの一文で締めるのがポイントです。
夏季休業のお知らせ文フルテンプレート2選
企業や店舗が夏季休業を案内する際には、フォーマルな書き方を意識します。
期間や対応日を明記しつつ、季節感のある挨拶を添えると柔らかい印象になります。
| タイプ | テンプレート |
|---|---|
| フォーマル(社外向け) | 盛夏の候、貴社におかれましてはますますご発展のこととお慶び申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 休業期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
| セミフォーマル(顧客・会員向け) | 炎暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
誠に恐縮ではございますが、下記の期間中は夏季休業とさせていただきます。 ご不便をおかけしますが、引き続きよろしくお願いいたします。 |
「盛夏の候」「炎暑の候」はお知らせ文との相性が抜群です。
フォーマルな文面でも、冒頭の一文に季節感を入れるだけで柔らかくなります。
社内・顧客メールに応用できる文例集
メールの場合は、文章を簡潔にまとめ、読みやすさを優先しましょう。
件名と挨拶のトーンを合わせることで、全体に統一感が生まれます。
| 件名 | 文面例 |
|---|---|
| 【お中元御礼】ご厚情ありがとうございます | 盛夏の候、日頃より格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
このたびはご丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。 暑い日が続いておりますが、引き続きよろしくお願いいたします。 |
| 【夏季休業のご案内】○月○日〜○月○日 | 大暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
誠に勝手ながら、弊社では下記期間を夏季休業とさせていただきます。 何卒ご了承のほどお願い申し上げます。 |
ポイント: メール文では1〜2文の挨拶+要件+一言の気遣い、が理想的な構成です。
お礼・案内・報告のすべてに共通するのは「相手への心配り」です。
形式だけでなく、相手を思いやる言葉を添えると印象がぐっと良くなります。
時候の挨拶の正しい構成と文章の組み立て方
時候の挨拶は、ただ季節の言葉を並べるだけではなく、文章の流れが大切です。
正しい構成を押さえれば、フォーマルでもカジュアルでも自然で心のこもった挨拶になります。
ここでは、7月下旬の挨拶を組み立てるための3つのステップと具体的な文例を紹介します。
書き出しの基本ルール(時候語+相手の健康+自分の近況)
書き出しの挨拶は、相手に「季節感」と「気遣い」を伝える部分です。
次の3ステップで組み立てると、どんな相手にも自然に響く文章になります。
| ステップ | 内容 | 例文 |
|---|---|---|
| ① 時候語 | 季節を表す言葉で始める | 大暑の候、盛夏の候、炎暑の候 |
| ② 相手の健康を気遣う | 相手を思うひと言を加える | 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 |
| ③ 自分の近況を添える | 軽い報告で親近感を出す | おかげさまで、私どもも元気に過ごしております。 |
この順番を守ることで、自然で流れのある導入になります。
「時候語 → 相手の気遣い → 自分の近況」=美しい冒頭文の黄金比です。
本文で自然につなぐ言い回し例
書き出しのあとに続く本文は、相手への感謝や近況報告を述べる部分です。
ビジネスでは「日頃の感謝」、個人宛では「最近の出来事」を簡潔に入れると印象が良くなります。
| タイプ | つなぎの例文 |
|---|---|
| フォーマル | 平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 |
| セミフォーマル | いつも温かいお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。 |
| カジュアル | 最近は夏の話題が多くなりましたね。お変わりなく過ごされていますか。 |
注意: 「季節の話題→感謝→本文」という自然な順序を意識しましょう。
急に本題に入るよりも、少し緩やかに展開した方が品のある印象になります。
結びの挨拶で印象を上げる定番フレーズ10選
結びの挨拶は、全体の印象を決める重要なパートです。
7月下旬なら、暑さを気遣う言葉や再会・継続への期待を添えるのが自然です。
| 分類 | フレーズ例 |
|---|---|
| フォーマル | 暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。 |
| フォーマル | 今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 |
| セミフォーマル | 厳しい暑さが続きますが、どうぞお体をおいといください。 |
| セミフォーマル | 今後ともよろしくお願いいたします。 |
| カジュアル | 暑い日が続きますので、どうぞご無理なさらずお過ごしください。 |
| カジュアル | またお会いできる日を楽しみにしています。 |
| カジュアル | この夏が穏やかで楽しい季節になりますように。 |
| 全般 | 今後のご多幸をお祈り申し上げます。 |
| 全般 | 暑さに負けず、元気にお過ごしください。 |
| 全般 | これからもどうぞよろしくお願いいたします。 |
結びでは「気遣い+願い」の2要素を意識すると、自然でやさしい文章になります。
冒頭と結びが美しいと、全体の印象が格段にアップします。
まとめると、理想的な文章構成は次のとおりです。
| 構成 | 役割 | 例文 |
|---|---|---|
| 書き出し | 季節+相手の気遣い | 盛夏の候、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 |
| 本文 | 感謝や近況 | 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 |
| 結び | 体調への配慮・今後の挨拶 | 暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。 |
ポイント: 全体のトーンを「季節感」「敬意」「温かみ」で統一すると完成度が上がります。
7月下旬らしさを伝える季節の言葉・描写アイデア集
7月下旬の挨拶で魅力的なのは、何といっても「季節感」です。
ただ「暑いですね」と言うよりも、自然や情景を一言添えることで、文章が一気に生き生きとします。
この章では、7月下旬を感じさせる自然・気候・行事などの言葉を紹介します。
気候・自然の表現(入道雲、セミ、真夏日など)
7月下旬の自然を表す言葉は、強い太陽や夏の空気をイメージさせるものが多いです。
手紙やメールに一言添えるだけで、読者の頭に夏の情景が浮かびます。
| カテゴリー | 表現例 | 使い方のヒント |
|---|---|---|
| 空・雲 | 入道雲、青空、真夏の日差し | 「入道雲が空に立ちのぼる季節となりました」 |
| 音・風 | セミの声、夕立、涼風 | 「セミの声がにぎやかに響く頃となりました」 |
| 風景 | 緑の木々、ひまわり、夏の空気 | 「ひまわりがまぶしく咲き誇る季節となりました」 |
具体的な季節描写を入れると、言葉だけで温度や空気が伝わります。
体調を気遣う言葉(やさしく伝える表現)
暑さの中でも、相手への配慮を忘れないひと言を添えると印象が柔らかくなります。
ただし、「健康」「病気」といった直接的な言葉は避け、やさしいトーンで表現しましょう。
| トーン | 表現例 |
|---|---|
| フォーマル | 暑さ厳しき折、ご無理のないようお過ごしください。 |
| セミフォーマル | 暑い日が続きますが、どうぞお体を大切にお過ごしください。 |
| カジュアル | 暑さに負けず、ゆっくり過ごしてくださいね。 |
注意:「体調」や「健康」などの医療的な表現は避け、日常的な言い換えで伝えるのが安全です。
やさしい言葉のほうが、心に残る挨拶になります。
イベントや風物詩の表現(夏祭り、花火大会など)
夏の行事を取り入れると、季節感が一気に増します。
地域の風物詩を思い起こさせる言葉は、読んでいて楽しい印象を与えます。
| テーマ | 言葉・フレーズ | 使い方例 |
|---|---|---|
| 夏祭り | 太鼓の音、夜店の明かり、提灯 | 「夏祭りの賑わいが待ち遠しい季節となりました」 |
| 花火 | 夜空の花火、夏の彩り | 「夜空を彩る花火に、夏の風情を感じます」 |
| 季節の行事 | 夕涼み、夏の便り | 「夕涼みの心地よい風を感じる頃となりました」 |
イベント名を出さずに「灯り」「音」「風景」などを描くと、フォーマルな文でも違和感がありません。
“情景を借りて心を伝える”のが上級の時候表現です。
7月下旬の挨拶に季節の情景を取り入れるだけで、文章がより豊かになります。
形式ばった文面でも、ひとつ季節の言葉を添えるだけで温度を感じさせる文章に変わります。
読んだ相手が「季節を感じる」挨拶、それが理想の時候文です。
7月下旬の挨拶で避けたいNGワードと注意点
いくら丁寧に書いても、使う言葉を間違えると相手に違和感を与えてしまうことがあります。
この章では、7月下旬の挨拶で避けるべき表現と、その理由をわかりやすく解説します。
「失礼にならない・時期に合う・安全な表現」を選ぶことが大切です。
使う時期を間違えやすい言葉一覧
時候の挨拶には「使うのにふさわしい時期」があります。
7月下旬は「梅雨明け直後から夏本番」にかけての時期なので、初夏や秋を連想させる言葉は避けましょう。
| NG表現 | 理由 | 代わりに使える表現 |
|---|---|---|
| 梅雨明けの候 | 梅雨明け直後(7月中旬)までの表現 | 盛夏の候、大暑の候 |
| 初夏の候 | 6月頃に使う言葉で、7月下旬は遅い | 炎暑の候、酷暑の候 |
| 立秋の候 | 8月上旬以降に使う表現 | 大暑の候 |
| 残暑の候 | 8月中旬〜下旬向け | 盛夏の候 |
「季節の切り替え時期」は特に注意が必要です。
迷ったときは“通年で使える表現”を選ぶのが安全です。
7月下旬なら「盛夏の候」や「大暑の候」が最も無難で、地域差にも対応できます。
相手との関係に合わない表現に注意
フォーマルすぎる表現や、反対にくだけすぎた言葉は相手を戸惑わせることがあります。
文体のトーンを「相手との関係性」に合わせることで、自然で好印象な挨拶に仕上がります。
| シーン | 避けたい例 | おすすめの表現 |
|---|---|---|
| 取引先・目上 | 暑いですね〜、お元気ですか? | 大暑の候、貴社におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 |
| 友人・同僚 | 盛夏の候、貴殿におかれましては… | セミの声がにぎやかになってきましたね。お変わりありませんか。 |
| お客様 | 厳暑の候、ご清祥の段…(古風すぎ) | 炎暑の候、日頃のご愛顧に心より感謝申し上げます。 |
“相手に合わせて言葉の硬さを調整する”のが上級者のコツです。
特にビジネスでは「少し丁寧すぎるくらい」がちょうど良いバランスになります。
フォーマル過ぎ・カジュアル過ぎを防ぐバランス調整法
表現が硬すぎると距離を感じ、柔らかすぎると軽い印象になります。
次の表を参考に、目的に合わせた適切なトーンを選びましょう。
| トーン | 特徴 | 使用シーン |
|---|---|---|
| フォーマル | 文語調、漢語中心、敬語強め | 企業間の手紙・公式文書 |
| セミフォーマル | 丁寧語+柔らかい言葉 | 顧客・知人宛ての挨拶状 |
| カジュアル | 話し言葉に近い、自然体 | 友人・身近な相手とのやりとり |
NGパターン: フォーマル文中に絵文字を入れる/カジュアル文で過剰な敬語を使う。
トーンの統一は、相手への敬意を示す基本マナーです。
言葉選びを少し意識するだけで、文章全体の印象が驚くほど変わります。
7月下旬の挨拶は、季節感と丁寧さの両立を意識して仕上げるのが理想です。
まとめ|7月下旬の挨拶は“思いやり+季節感+一言の工夫”
ここまで、7月下旬にふさわしい時候の挨拶や例文を紹介してきました。
最後に、挨拶文を美しく仕上げるためのポイントを整理しておきましょう。
思いやり・季節感・一言の工夫——この3つを意識するだけで、どんな相手にも好印象を与えられます。
初心者でも美しく書ける5つのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 相手に合わせたトーン | ビジネス・友人など、関係性に応じて文体を調整する。 |
| ② 時期に合う時候語を選ぶ | 7月下旬なら「大暑の候」「盛夏の候」「炎暑の候」が定番。 |
| ③ 季節の情景を添える | 入道雲やセミの声など、夏のイメージを一言加える。 |
| ④ 結びの言葉で印象を整える | 「ご自愛ください」など、やさしい一文で締めくくる。 |
| ⑤ 丁寧さより心を大切に | 完璧さより、気持ちが伝わる表現を心がける。 |
特に大切なのは、「誰にどう伝えたいか」を意識すること。
文体の丁寧さよりも、「この人に喜んでもらいたい」という想いが伝わる文章が、一番印象に残ります。
この記事の例文を活かすチェックリスト
挨拶文を書くときに役立つ、実践用チェックリストを用意しました。
| チェック項目 | 確認 |
|---|---|
| 1. 時期に合った時候語を使っているか? | □ |
| 2. 相手の立場に合う言葉遣いか? | □ |
| 3. 季節感を出す具体的な描写が入っているか? | □ |
| 4. 結びの挨拶でやさしく締めているか? | □ |
| 5. 誤字・不自然な表現がないか? | □ |
この5つを確認すれば、どんな挨拶文でも安心して送ることができます。
「正しい+伝わる」このバランスこそ、上質な文章の条件です。
次に読みたい「8月上旬の時候の挨拶」への導線
7月下旬の挨拶をマスターしたら、次は8月上旬の「立秋の候」などの表現に進むと、さらに季節の文が豊かになります。
たとえば、8月上旬は「残暑お見舞い」「立秋」「涼風」などの言葉が主役です。
季節の変化に合わせて言葉を選ぶことで、あなたの文章力がぐんと上達します。
| 季節 | 代表的な挨拶語 | 使う時期の目安 |
|---|---|---|
| 7月下旬 | 大暑の候、盛夏の候 | 7月23日〜8月5日 |
| 8月上旬 | 立秋の候、残暑の候 | 8月7日〜8月15日 |
季節の言葉を丁寧に選ぶことは、相手への敬意のあらわれでもあります。
次の季節も、心のこもった文章で季節のご挨拶を届けてみてください。